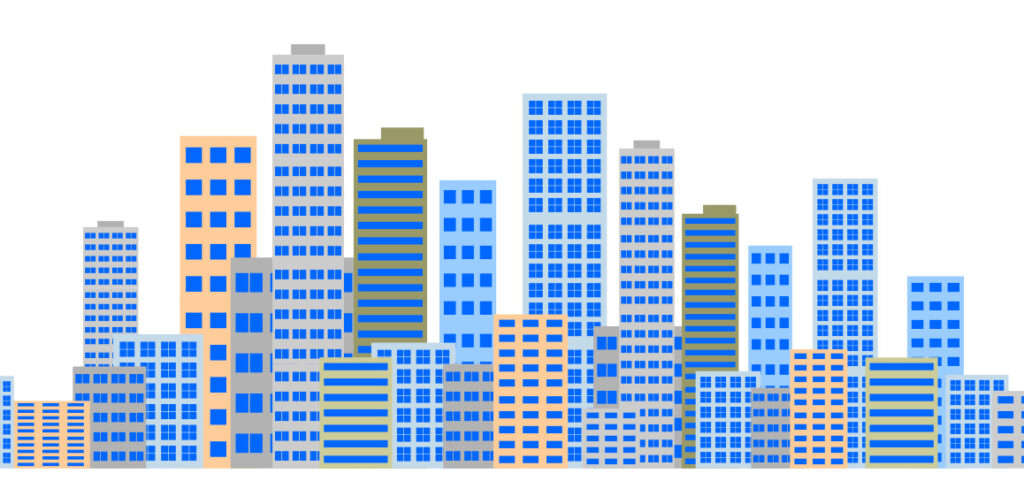「コロナ禍で社員の帰属意識が低下」「いや、そもそも若手社員の帰属意識が低下している」そんな話をよく聞くようになりました。では実際のところ、ビジネスにおける帰属意識とは何でしょうか? また、それが低下すると何が問題なのでしょうか?
なんとなくは理解していても、「これこそが弊社の課題である!」と断言して改革に乗り出している方は、それほど多いのではないでしょうか?
ここではそんなビジネス、会社組織における帰属意識について解説します。
社員のやる気を高める帰属意識とは何か?
帰属意識とは、もともとは心理学の用語で会社に限らず、「ある集団に所属し、構成しているという意識や感覚」とされています。ただ、一般に帰属意識と言った場合には、「その集団に所属し続けたいという意欲や愛着」を意味します。
つまり、会社組織で言えば、ただ雇用関係にあるだけでは「所属」しているだけです。しかし、「帰属」となると、その集団に帰りたい、その集団に居続けたいと願っていると言えます。
このその集団・会社組織に居続けたいという意識・欲求がなくても、給与が支払われている以上、構成員たる従業員はある程度仕事をするでしょう。しかし、その雇用関係が完全に金銭だけのものになると、かんたんにその構造が崩れてしまうということは想像に難くありません。
帰属意識が低下して起きる問題
帰属意識が個人的に、あるいは集団的に低下した場合、各所でさまざまな問題が発生します。ただ、それらはひとことで言い表すこともできます。
やる気・士気が低下する
すこしカジュアルに表現すると、「若手の帰属意識が低い」と「若手のやる気がない」と言い換えることもできるかもしれません。
とはいえ、やる気(モチベーション)・士気(モラール)の低下に関しては帰属意識の低下だけが原因とはいえません。やる気が低下するようなことが発生すると(上司に理不尽なお叱りを受けた、給与が十分でない、評価されていない……など)、帰属意識が低下し、さらにやる気も低下する……と考えると理解しやすいと思います。
また、やる気の低下は周囲の従業員にも影響し、個人のやる気の低下から従業員全体の士気の低下にもつながっていきます。
そして、やる気・士気が低下して帰属意識が低下すると、さらに以下のような問題が発生しやすくなります。
従業員が離職しやすくなる
一般に従業員の離職率や、定着率といった言葉で表現されます。ただ、明確に指標として使われている計算式はないようです(全社で計算するか、期間で計算するか……など立場によって基準が変化するからでしょう)。
「新入社員の帰属意識が低い!」とされるのはまさにこの現象でしょう。たとえば令和1年度の新入社員10人が、令和2年度には5人、令和3年度には3人……と減っていったとすると、令和2年度時点では離職率・定着率ともに50%, 令和3年度時点では離職率70%, 定着率30%と表現することができます。これを、10年前のデータと比較すれば、たしかに近年の新入社員の離職率が高いと言えるでしょう。
さらに、おもな待遇や業務内容などが変わっていなければ、帰属意識が低下していると判断できるかもしれません。
従業員同士の助け合いが低下する
帰属意識の高い従業員にとっては、自分が帰属する集団が存在し続ける、発展することは自分にとっての喜びでもあります。たとえば、家族や友達にいいことがあれば嬉しいですし、スポーツの世界大会で日本人が優勝すると、なんとなく嬉しいのはそれぞれの集団に対して帰属意識があるからだ、と言えます。
そのため、帰属意識の高い従業員については、他の従業員が困っていたら特別報酬が期待できなくても手助けをしたり、仕事を教えたりという行動が期待できます。一方で、帰属意識の低い従業員の場合には、そういった行動は期待できません。それどころか、成果による報酬のために積極的に邪魔をするかもしれません。
実は、成果報酬による弊害というのは、従業員の帰属意識が高ければある程度防ぐことも可能なのです(完全にではないですが)。
社内環境が悪化する
社内美化に対する意識が低下したり、備品を粗雑にあつかうことも増えてしまいます。
なんとなくオフィスが荒れてきた……といった徴候がある場合は注意が必要です。
報連相の不徹底など、コミュニケーションに不備が起きる
帰属意識は同じ集団に居続けたい、仲間であるという認識ですから帰属意識が低いと当然、仲間ではなくただの「他人」に対するコミュニケーションとなります。そのため、先に記載した助け合いのような善意のコミュニケーションは発生しにくくなります。また、そもそもコミュニケーションにかかる心理的コストが増大するために、コミュニケーションを怠りがちになります。
帰属意識を低下させないためには?
帰属意識ややる気は、「気持ちの問題」でもあります。
そのため、先に記載した帰属意識ややる気が低下しておきる現象を放置すると、問題を抱えた従業員だけでなく、周囲に対しても悪影響を与えてしまいます。
たとえば、上司に当たる人物が何か問題を抱えて、部下とのコミュニケーションを怠ってしまった場合のことを考えましょう。そうすると、部下は当然、不満を抱えますし、十分なコミュニケーションをとれない組織に対して愛着を抱かなくなります。
このように、全体的な帰属意識を低下させないためには、問題の発生を見逃さず、まずは他の従業員に広がらないように対応する必要があります。
また、帰属意識を低下させないためには、ハーズバーグの二要因理論、動機づけ・衛生理論にもとづき、不満足の要因となる衛生要因の改善が有効です。やたらと「やる気を出そう!」とするのではなく、まずは給与や労働環境などで不満足を解消するといいでしょう。
働き方や、福利厚生の改善といった、人事・労務部署の腕の見せ所と言えます。
帰属意識を向上させるには
ハーズバーグの動機づけ・衛生理論にもとづいて、マイナス要因を取り除いた後は、今度は同理論で言えば「動機づけ」の強化が重要になります。
ただし、動機づけ要因については、帰属意識の向上という観点だけで見れば、特に「達成」や「承認」といったより人間的な部分の比重が大きくなります。大きな昇進などがなくても、十分に帰属意識は向上させることができます。
マズローの5段階欲求理論でいえば、社会的欲求を満たすことで帰属意識が向上するといえます。一方で、その上位に当たる承認欲求に至るには、十分社会的欲求を満たし、組織への帰属意識を向上した上で着手すべきと言えますね。
帰属意識の向上で、バッジ・社章ができること
会社バッジ、社章はまさしくその会社・組織に所属するという証明でもありますし、無条件の承認でもあります。組織への所属とは、本来、目に見えないものではありますが、バッジを身につける、受け取ることで目に見えて手に触れられる証として使用できます。
また、従業員規模の大きい会社では、お互いの顔をしらないということはよくあります。社内に入館する際には、社員証を首から提げていなければならない会社も多いですが、一方で個人情報が記載されているために、社外ではしまっておく方が一般的です。しかし、会社のバッジであれば、どこでも身につけておけるので、従業員同士の目印となりコミュニケーションの促進が期待できます。
また、とくにサービス業のコンタクトパーソネルで重視されるインナーマーケティング・インターナルブランディングという概念があります。これは、「組織やブランドの目標を、従業員ひとりひとりの目標とするために行うブランディング手法」です。つまり顧客にブランド価値をマーケティングで提供する前に、まずは従業員に浸透させます。
このブランド価値を表現し、従業員に自覚的になってもらうためにも、バッジ・社章は有効なツールとなっています。
なによりも、通常の社員証とは異なり、社章であるために従業員ひとりひとりを大切にする会社であれば、そのメッセージとともに会社バッジを配布することで、マネジメントの考えを従業員ひとりひとりに伝え、帰属意識の向上に役に立つでしょう。
[service title=”お問い合わせ” icon=”icon: sort-amount-asc” icon_color=”#ffee03″ size=”32″]バッジ専門店では、多種多様なバッジ・社章の製作を承っています。 帰属意識・組織へのロイヤリティーを高める特別素材、特別仕様の製作も可能です。お見積もり・お問い合わせは無料ですので、お気軽にご相談ください。 [button url=”https://www.shasho-original.com/contact/” target=”self” style=”3d” background=”#183679″ color=”#FFFFFF” size=”7″ wide=”no” center=”yes” radius=”auto” icon_color=”#FFFFFF” text_shadow=”none”]お問い合わせ[/button] [/service]